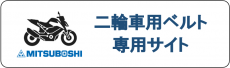Sustainabilityサステナビリティ
リスクマネジメント
三ツ星ベルトグループは、「持続可能な企業」を目指すに際し、リスク管理の重要性を認識し、継続的に管理システムの改善に取り組んでいます。リスク管理の手法として、ISOの要求事項である「リスクと機会」の考え方を採用し、それをベースにし、戦略、方針、計画、目標を設定し、リスク管理を効果的に展開して事業活動を行っています。
リスク管理の考え方
リスク管理と事業活動の統合
三ツ星ベルトグループは、リスク管理活動のアウトプットを、あらゆる事業環境の変化に対して安定して持続することのできるESG経営の実践に効果的に展開し、持続可能な社会の実現に貢献する。
リスクの範囲
三ツ星ベルトグループのリスク管理活動において、財務的な悪影響と同等に、人権、コンプライアンス、安全衛生、環境、品質等に関する非財務的な悪影響も取り扱う。
実施責任者
三ツ星ベルトグループのリスク管理活動は、実施責任者を明確にして実行する。
リスク管理の実行者
三ツ星ベルトグループのリスク管理活動は、全ての役員、従業員により実施され、あらゆる事業活動が対象となる。また、リスク管理の有効性を確保するため、事業環境に係る情報は常に最新とし、特にステークホルダーからの情報入手に留意する。
リスク管理システムの維持・改善
有効に機能するリスク管理システムを構築・維持・改善しリスク管理を実行する。
情報開示
リスク管理に関する情報は全てのステークホルダーに対して適時適切に開示する。
管理体制
三ツ星ベルトグループでは、当社の事業活動において、事業に対するインパクトが大きく、グループ全体で取り組むべき課題(重大リスク)に対するリスク管理活動の監視・評価を目的として、また、グループ全体のリスク管理体制の維持・発展を目的として、リスク管理委員会※が設置されています。
※委員長 : 社長が指名する役員 / 委員 : 全事業部門・関係会社の責任者
リスク管理委員会は、毎年度、重大リスクおよびその対応組織、責任者、目標、計画を決定し、原則年2回、対応組織の責任者から対応状況の報告を受け、その内容を審議します。重大リスク選定における決定内容、対応状況に対する審議内容は、都度、社長および取締役会に報告されます。また、リスク管理委員会は、三ツ星ベルトグループのリスク管理活動を、制度面(方針、規程・要領等)から牽引する役割も担っています。
各事業部門・関係会社が取り組むべきと判断した課題(重大リスクを含むそれぞれの経営環境で発生する様々なリスク)に対するリスク管理活動は、各事業部門・関係会社の責任者が、年度方針書に対応部門、責任者、目標、計画を明確にし、社長の承認を得たうえで実施され、当該責任者が実施状況の日常的な監視・評価を行います。原則年1回、リスク管理活動の実施状況は、事業部門・関係会社の責任者から社長および取締役会に報告され、審議のうえ、必要に応じて指示がなされます。
リスクの評価
三ツ星ベルトグループでは、取り組むべき課題(リスク)を選定する過程において、事業活動に対する影響度と発生可能性の2軸を使って、リスクの評価を行っています。リスク管理委員会で重大リスクを選定する場合の評価尺度は、影響度(大:10億円以上、中:1~10億円、小:1億円未満)、発生可能性(高:1回以上/年、中:1回 /2年、低:1回未満/10年)となっています。各事業部門・関係会社では、その経営規模に対応させ、評価尺度を取り決め、リスクの評価に活用しています。
2024年度の活動では、前年度に引き続き、リスク管理委員会において事業部門・関係会社の全責任者が参加するリスクアセスメントを実施し、その結果をもとに、三ツ星ベルトグループが取り組むべき重大リスクを特定しております。
リスクの把握
2024年度のリスクアセスメントの結果、リスク管理委員会において以下の2点を重大リスクとして選定しました。① 自然災害・大規模事故による自社の事業活動の停止、② 同様の要因によるサプライヤーの事業活動の停止。これらに対しては、対応施策、実行組織、責任者、目標、計画を定め、実施状況を継続的に監視・評価してまいりました。
また、アセスメントの過程で重大リスクの候補として挙がったEV化、景気変動、情報セキュリティ、経済安全保障等については、他の会議体や委員会において対応状況の監視・評価を行っております。
| 特定された重大リスク | 実績 |
|---|---|
|
グローバルな生産体制の再編によるリスク分散に加え、国内では倉庫(ロケーションと在庫量)および運送方法(ルートと運送業者)の両面から物流体制を見直しました。 また、事業継続計画(BCP)は国内外の生産拠点にとどまらず、営業拠点にも活動を拡大しています。 |
|
主要原材料に加え、副資材や外注加工先についても、複数社からの購買を進めています。また、主要取引先には事業継続計画(BCP)の策定・運用を要請し、その実施状況については年1回の頻度で調査を実施しています。 |